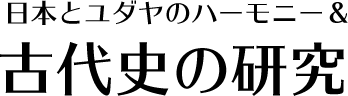邪馬台国を理解するにあたり大事なことは、古代の識者は今日私たちが想像する以上にその当時、距離や方角に関するかなり正確な地理情報を持っていたことを再認識し、その原点にはイスラエル南ユダ王国の民の存在があったことに気が付くことです。イスラエルの首都エルサレムは、地中海沿岸から山々を越えて辿り着く内陸の都であり、イスラエル系の渡来人は、水源に恵まれた「東の島々」、「神の山」を求めて日本列島まで旅をしてきました。また神宝がエルサレム神殿に厳重に保管されていたように、イザヤの預言書を頼りに、新天地においても神宝は命をかけて守らなければならなかったのです。よって邪馬台国の地が、沿岸の無防備な地域や、大国に隣接する地に置かれるとは到底考えられないのです。これらの疑問点を払拭するためにも、邪馬台国という古代国家を考えるにあたり、その歴史的背景だけでなく、関連する諸条件、視点、考え方を今一度見直してみることにしました。
目次
前提1:史書の歴史観と背景
邪馬台国についての記述が含まれる複数の史書を理解するにあたり、その歴史的背景に留意することは極めて重要です。魏志倭人伝が含まれる「三国志」は280~290年に編纂されました。卑弥呼の時代から既に半世紀近くが経ち、倭国ではちょうど応神天皇が即位し、大和朝廷が産声を上げ始めたときです。それは中国側から見れば、それ以降、倭国からの情報が途絶える「歴史の空白」の始まりでもあります。三国志に倭人伝が編纂された理由は、魏の倭に対する出兵であり、卑弥呼の時代からもさほど年代を経ていないことからしても、三国志は3世紀ごろの歴史観によってまとめられていると言えます。しかし何故、倭に対して魏が出兵することになったか、また2世紀後半から3世紀にかけて生じた倭国の混乱が何故起きたか、それがどう中国に影響を及ぼしたかなど、不透明な部分は多々残されたままです。
もう1つの史書、後漢書倭伝の内容は、前漢の武帝が衛氏朝鮮を前108年に滅ぼした後に倭国の使者が漢を訪れた話から始まり、最後に女王国の話で終わっています。しかし後漢書が編纂されたのは三国志より100年以上も遅く、398年から445年ごろです。つまり実際の後漢の時代から後漢書が編纂されるまで、4世紀前後も時を隔てているのです。それ故、後漢書は三国志の記述を多分に参考にしただけでなく、その後の倭国の展開に関する歴史についても、三国志より多くの情報を得ていた可能性があります。更に後漢書では、魏の出兵による倭との対立が背景にある三国志とは異なり、むしろ孔子の言葉を引用しつつ、東夷について高い評価がなされていることも注目に値します。また、三国志、後漢書から更に年代が隔たる隋書の編纂は7世紀となり、大和朝廷の発展を目の当たりにした上で編纂され、当時の遣隋使の話で終わっています。それ故、隋書の編者にとって邪馬台国は遠い過去の歴史として捉えられたことと思われ、また、倭国に対する編纂者の見方には、大きな相違があったとしても当然のことでしょう。
異なる時代に編纂された史書は、昔からの言い伝えや、見聞きしたこと、今起きていること、その他、諸々の記述を引用してでき上がります。特に複数の史書が網羅する倭国の歴史は長期間に及び、後漢書の武帝の記述から隋書の遣隋使に至るまで、およそ750年間に渡る倭国の歴史を記録しているのです。これらの背景には、実際に資料を提供した中国の識者や、東夷伝の編集に関わるグループの存在、そしてさまざまな参考文献の存在があったことでしょう。しかも時代を経て記載されていることから、外部環境や政治的背景の影響も受けやすかったに違いありません。よって史書の内容を正しく理解するには、それらの点も見極める必要があります。
前提2:イスラエル系渡来人の影響
邪馬台国を考えるにあたり、もう1つ大切な点は、邪馬台国の民がどこからきたか、ということに留意することです。前述したとおり、前2~3世紀以前の古代日本においては、縄文人を中心とした原住民に加え、前7世紀より西アジアから移住してきた少数の南ユダ王国部族の存在があったと考えられます。しかしながら、それらの民の存在は列島の外部に知られることはなかったようです。史書の中でも最古と言われ、前漢の時代、およそ前104年に司馬遷が着手して前91年ごろに編纂を完成した「史記」の中に含まれる朝鮮伝にも、倭国についての記載は全くありません。
それから170余年を経た後漢の時代、班固が82年に編纂した「漢書」に初めて、倭国に関連する記述が短く見られ、「それ、楽浪の海の中に倭人が住んでいて、分かれて百余の国をつくり、毎年使者を送り、捧見している」と記載され、三国志などにも同様の記述が見られるようになります。つまり、東夷とも呼ばれるイスラエル系を中心とする東アジアからの渡来人が、朝鮮半島を介して大勢押し寄せ始めたと考えられる前2世紀ごろを起点として、それから200年余りの間に、突如として倭国と呼ばれる島国に、100余りの国が歴史に姿を現したのです。これはまさに、無数の渡来人が到来した結果と言えます。
史書が証するもう1つの重大な事件は、後漢末の147年から189年ごろ、「倭国はたいへん混乱し、たがいに戦い、何年もの間、主なきありさまであった」という記述の内容です。これは、大勢の渡来人が部族ごとに100国以上に分かれて各々統治をし始めたものの、移民の流入がピークに達し、緊張感が高まった結果と言えます。また、当時の渡来人は西アジア系の東夷だけでなく、中国系の人々も多く含まれ、それまでのユダヤ教の解釈を一新してキリスト教という新しい宗教概念を携えた秦氏一族が、朝鮮半島から一気に到来してきた時期でもあります。秦氏の存在は、各地でさまざまな宗教紛争を起こしたに違いなく、倭国混乱の主要因の1つと言えるでしょう。特に、その政治経済力は並大抵のものではなく、到来は他部族に遅れをとったものの、入国後は欲する領土を思うままに奪取し、多くの紛争を倭国に巻き起こしたと考えられます。そして短期間に秦王国とも呼ばれる拠点を築き上げ、その存在は中国にまで知れ渡るほどになりました。それが「東して秦王国に至る。秦王国の人は中国人と同じである」と隋書などに記されたる所以です。秦氏の存在は、その後の日本の歴史を理解する上で、極めて重要な存在となります。
前提3:山上を目指したイスラエルの民
古代日本社会においては不思議なことに、住みやすい平野ではなく、標高の高い山々に人が居住するという高地性集落の現象が見受けられ、特に四国、中国地方ではその傾向が顕著に見られました。しかし、人が居住しやすい平地がなかったわけではなく、実際には随処に広大な平野が広がっています。それでも高地性集落が栄えた理由は何故でしょうか?
前7世紀、日本を訪れた初代のイスラエル系渡来人は、イザヤ書の預言に従って東の島々である日本列島を見出しただけでなく、同預言書の教えに従って、山々の頭として聳え立つ「主の神殿の山」を求めて各地の山々を登りつめ、その周辺に集落を作り続けたと考えられます。よって、イスラエル系渡来人が訪れたと考えられる諸地域では、特に四国、中国地方、そして近畿や中部地方に至るまで、いつしか高地性集落が広がっていきます。邪馬台国もその高地性集落の1つではなかったかと考えられる裏付けが、実は史書に記されています。
史書の記述によると、邪馬台国には牛や馬、羊などの家畜が存在しないことが明記されています。もし、邪馬台国が平野に位置していたならば、そこに家畜が存在しないということは、古代日本社会においても考えにくいことです。また、高地性集落においても、実際には多くの動物が飼育される牧場が存在することが知られています。では何故、邪馬台国には家畜が存在しなかったのでしょうか?その答えを聖書に見出すことができます。祖国を失ったイスラエルの民は、東の島々に聳え立つ「神の山」を求めて日本列島に渡来して来ました。よってイスラエル人にとって、日本の山は聖なる存在だったのです。その聖なる山について、旧約聖書の出エジプト記34章には、「山のふもとで羊や牛の放牧もしてはならない」と明記されているのです。モーセが登ったシナイ山が聖なる山であったように、新天地の拠点に聳え立つ山も同様に聖なる山として、家畜を排除することが取り決められたのでしょう。また、神の宝を安全に保管し、外敵から守るためにも、神の山は防御に優れた地形を有さなければなりません。そのようなイスラエル系民族の念願を叶えた聖なる神の山が存在したからこそ、その周辺には長い年月をかけて集落ができ上がったのです。こうして、山上の国家となるべく、邪馬台国の土台は長年にわたり培われていくことになります。
魏志倭人伝をはじめ、史書には邪馬台国に関する地理や文化、人口に至るまで、さまざまなデータが明記されています。当時の科学、天文学、地理学に関する知識レベルは、現代人が思うほど原始的ではなく、むしろ優れているが故、史書の記述は歴史の謎を紐解く上で、大変貴重なデータとなります。エジプトやメソポタミアなどの古代文明を振り返りますと、そこには現代の科学でも計り知れないほどの優れた文明が存在していたことがわかります。特に測量と幾何学、天文学、そして地理学については、西アジアに散在する著名な遺跡の多くが、その形状や立地条件などから、それらが詳細にわたり緻密な計算によって当初から設計されていたと考えられ、そのレベルの高さには目を見張るものがあります。その西アジア文化圏で育まれた高度な文明は、橋渡し役となったイスラエルの民を中心とする西アジアからの移民によって東アジアにもたらされ、その影響を多分に受けながら、中国ではメソポタミア文明に匹敵する黄河・長江文明などが育まれました。優れた中国文化の基には、西アジア古代文明の知恵が息吹いているからこそ、その文明の延長線に登場する史書にも優秀な識者や編纂者が携わり、各種データの正誤性を確認した上で、最終的に編纂されたと考えられます。よって、史書に記載されている邪馬台国までの道のり、距離、方角をはじめとし、地形やその他、文化的背景に関するデータの信憑性は高いと言えます。
50万規模の人口に適する広大な土地
邪馬台国の人口は、7万世帯と史書には記されています。これは邪馬台国の領土が広大であり、その規模は中国における郡にも匹敵するほどの、大きな固有の領土であったことを意味しています。例えば後漢初期に編纂された漢書地理志によると、秦の時代に設置された遼東郡には、前漢の時代、5万5千972の戸数があり、人口は27万人を超えたという記述があります。また楽浪郡には6万2千812戸が存在し、人口は40万人、また玄兎郡には約4万5千戸、22万の人口があったことが窺えます。楽浪郡よりもさらに多い7万戸数を邪馬台国が誇示したということは、その人口は30万人を下ることはなく、おそらく40~50万人に達していたと考えられます。楽浪郡の面積は九州の半分を優に超え、遼東郡や玄兎郡に至っては九州全体よりもさらに大きいエリアを占めていました。それ故、邪馬台国の人口を考慮するならば、おそらく楽浪郡に匹敵するほどの広大な領土を治めていたと想定できます。
前提5:高地性集落から誕生する山上国家
邪馬台国に行くために、水行と陸行を交互に繰り返すという難解な記述についても、それが長年にわたる旅の経験則から、目的地まで最も早く到達できる旅程として、航路・陸路に分かれた渡航経路が導き出されたからに他ならないと考えることで、理解の幅が広がります。その道程を史書の記述を文字どおりに理解するならば、邪馬台国の場所とは朝鮮の帯方郡から狗邪韓国まで海岸沿いを旅した後、対馬、壱岐を経由して倭の国の末慮に着き、そこから陸上を東南へ500里、100里、そして東へ100里、都合700里歩き、再度船で20日と10日、都合30日航海し、更に陸上を1ヶ月歩いて邪馬台国に辿り着くことになります。つまり、対馬、壱岐を過ぎて倭の国の沿岸に着いた時点から、さらに2ヶ月以上も水行と陸行を繰り返して旅しなければ辿り着けないほど、遠い所に存在したのです。しかも、40~50万人もの大人口を有する領土であり、島を一周すると5千里となり、島の東側には海を千里渡ると他の島が存在するということです。これらの記述から、邪馬台国が山上の国家であるようなイメージが浮かび上がってくるのではないでしょうか。農耕作にも適している平野部が目の前に広がっているにも関わらず、わざわざ山上を目指した理由は軍事的目的ではなく、むしろ、宗教的な背景が第一にあったと考えて間違いないでしょう。そしてイスラエル系渡来人が聖なる山を求めて渡来し、山上を目指して移住し続けたことにより、いつしか山上に国家の骨組みができ上がり、邪馬台国が歴史に姿を現すことになったのでしょう。
山上に国家が生まれる基には、高地性集落の存在が考えられます。西日本でも特に香川県などの中部瀬戸内には、高地性集落が存在したことは周知の事実です。つい先日、筆者が四国の奥伊祖を訪ねた際、山奥の急斜面に添う道路を登り続けると、一人の老婆が畑仕事をしていたのが目に留まり、声をかけてみました。もう80歳近いでしょうか。その方に、奥伊祖の昔がどんな様子だったのかを聞いてみました。すると、奥伊祖の周辺でも明治時代までは、山の高い部分に広大な牧場が存在していたことを話してくださいました。ところが明治維新以降、若い男性がどんどんと地元を離れて都会に出稼ぎに行くようになったため、農業や畜産業を営む男性が激減してしまい、牧場を存続することが難しくなり、それをきっかけに国家の方針に従って牧場をつぶし、そこに杉を植えたということでした。皮肉にもその結果、スギ花粉症に悩む人が増えて、困っているという話でしたが、わざわざ住みにくい山奥の高地に居住するという行動の背景には、おそらく宗教心があるに違いなく、よって、高地性集落の存在と邪馬台国とは確かに因果関係があると考えられます。
前提6:史書における距離感を理解する
後漢書や魏志倭人伝(三国志)など、史書の数々には距離を記す単位として「里」が用いられています。そのため、1里の距離がどの程度であるかを理解することが重要です。中国では時代によって「里」の長さが異なり、長里と短里に分かれています。まず、秦から漢の時代にかけては距離を表わす基準を馬の歩長にかけて考え、360歩をもって1里とし、これを長里と呼んだようです。その馬の一歩を約1.5mと仮定すると、1里はおよそ540mという計算になりますが、複数の地理事例から検証すると、1里あたりの距離は430m前後の計算になることから、歩幅の解釈がおよそ1.2mであったのかもしれません。いずれにしても、長里の距離はおよそ、400~500mの範疇に収まるようです。
魏、晋の時代でも長里は距離の単位として継承されつつも、やがて身近な距離を測るための単位として、人の歩幅を基準とした短里が頻繁に用いられるようになりました。長里が大まかな長い距離を測るために馬の歩幅を基準としたのに対し、短里は目先の建造物や近距離をより正確に表現するために用いられ、その距離は1里が70m前後から、長くても90mまでと考えられます。実際には、秦の時代を遡り、周代においても「論語」や「孟子」は短里で書かれ、また、四書五経などにも短里が採用されていたことから、魏の時代において、一昔前に使われていた距離の単位が復活したと考えることもできます。
「千里眼」という有名な言葉がありますが、「魏書」楊逸伝の「楊使君千里眼あり」という表現に由来しています。もし千里が長里ならばおよそ400~500kmとなり、単里ならば70~80kmになります。この「千里」という表現が、遠くまでも見渡すことができるという人間の視力の限界点を語っているとするならば、単里で考えた方がより、現実味がわいてくるのではないでしょうか。例えば韓国の南岸から対馬は、およそ千里と魏志倭人伝に記載されていますが、空気のきれいな天気の良い日は、実際に対馬の山上をはるか彼方に見ることができると言われています。つまり千里眼は単里で解釈した方が、人の目で遠くを見られるおよその限界点であることから、より理解し易いと言えるでしょう。
また、孔子の時代では単里が一般的に使われ、孔子の弟子も同様に単里を用いていたと考えられるだけでなく、「孔子家語」が編纂された魏の時代でも単里が使われていたことは注目に値します。歴史書としての価値を極めた一連の史書も、諸子百家の影響を強く受けた識者らが核となって編纂が行われたと想定されるため、ごく当たり前に単里が使われていたようです。こうして後漢書や三国志では単里が用いられ、その距離がおよそ70mであるという前提で記述内容を見直すと、魏志倭人伝をはじめとする史書の内容がより明確になります。
前提7:古代の海上渡航ルートを検証する
邪馬台国の位置を見極めるにあたり、見落としがちなのが、日本列島周辺における古代海上交通の航路です。海路が確立される経緯としては、まず列島外部から船が漂流、または着岸し、船が寄港するに相応しい地形、その他、内陸の立地条件を見極めることから始まったと想定できます。そして徐々に行き来が繰り返され、また内陸の拠点に人が住み始めることにより、周辺が港町として発展したのでしょう。
しかしながら、船による航海はときに困難を極め、特に帆船は渡航条件の変化から転覆し易く、多くの危険をはらんでいたことが知られています。18世紀に書かれた「増補日本汐路之記」でさえ、「船は汐に添い、風に委ねて人力の届ざる所、特に水脈の浅深を記憶、風を知り雲を知るともまた暴風発起することあり」と、船旅は一喜一憂の連続であることを記しています。よって、機械船を用いない帆船で渡航していた時代は、常に雨風という悪天候と潮の流れに左右されるため、危険を察知すればすぐに停泊できる陸地を見出すことが重要課題でした。そして頻繁に陸地に着岸しては、そこで水や食料の補給も随時行っていたのです。

日本列島周辺の潮流中でも海上航行に不可欠なのは、潮の流れを理解することです。日本列島近海を流れ抜ける「黒潮」は有名ですが、この大きな潮の流れは赤道付近の北東恒風帯を原点として、台湾東部から八重山諸島を筆頭とし、南西諸島に並ぶ島々の位置に添うように北東に向かって流れています。その後、四国、本州沿岸を北東へと進み、そこから三陸沖に達して東方に抜け去ります。その黒潮の流れは大変に強いことから、それが沖縄界隈では昔から、「島から出ることはすべて「旅」といわれてきた」 と語られてきた所以です。黒潮は九州南部から2分し、西側に分岐した流れは九州の西を北上し、済州島と長崎の間から壱岐、対馬間を通り抜けて、日本海に向かいます。そしてこの対馬暖流と呼ばれる流れは、青森の津軽海峡にまで達し、そこから太平洋側に向かって今度は、三陸沖を南下します。そして太平洋側からは、九州の南から列島沿いに北上してくる黒潮の流れとぶつかり合うのです。
「海上航行の基本的な技術はやはり潮と風にうまくのること」 であり、この黒潮の流れに乗って当初、帆船が南方より日本列島に到来したと考えられます。このように潮の流れに乗れば、山口県の漁師の間で語り継がれてきた「二日走り」にあるように、南風の助けを借りて、たった2日でロシアのウラジオストクまで辿り着くことも可能だったのです。また、偏西風に乗ると、太平洋側で難破漂流した船が、アメリカ大陸まで流されることも珍しくありませんでした。これらは潮の流れに逆らう航海は、大変な労力を伴うものであることを意味しています。また、潮の流れに加え、季節風の向きも重大な要素です。日本海方面の風向きと気圧配置は、1年を通して定期的に変化することが知られています。秋から冬、そして春から秋とでは風向きが変わることも、海上航海に多大な影響を及ぼします。航海者は経験則から、南系の季節風と、北系の季節風を上手に使い分けることが不可欠だったのです。
これら複数の要素が黒潮の流れと絡んで渡航条件に大きな影響を及ぼします。日本列島の周辺には、船が難破し易い危険な個所が多々存在し、それらは「海の難所」と呼ばれ、知られるようになりました。例えば九州の筑前宗像沖の難所は古代、中世を通じて航海者より恐れられています。凪の日でも潮の満ち干により、突如として急流のように潮が流れ、時化の日は、風向き次第で怒涛のごとく逆巻き、玄界灘で一番の難所となるため、近くの浜辺には難破船の漂着物が数多く打ち上げられてきたことで有名です。その漂着物の量があまりに多く、宗像神社の「本社・末社合わせて70余社の修理用途を、すべて近くの葦屋津、新宮浜に打ち上げられる難破船の漂着物をもって充当」していたことが記録に残っているほどです。
筆者も時折、徳島の小松島港から30フィートの機械船で海の旅に出向くことがあります。いざ自分が四国周辺の海を航海してみると、当初の想定よりも航海が難しい日が多いことがわかりました。天候に恵まれて視界も良く、無風状態で「べた凪」とも呼ばれる海が穏やかな日ですと、エンジンをフル回転して楽々と30ノット(地上速度で時速約55km)で快適に航海することができるのですが、そのような日は稀です。実際には、ちょっとした風向きの変化で海が荒れ始めることが多く、風が多少吹く程度で海の波が突如として高くなることがあります。また季節風と潮流の絡みだけでなく、ときには海に流れ込んでくる川の流れと潮の流れが交錯するエリアでも海流が複雑になり、海の難所となり易いのです。例えば四国の東沿いは、淡路島方面から南方に下る潮の流れが強く、それに加え、冬場になると北西風が強く吹くため、それに逆行する形で北に向けて航海することは、エンジンを搭載した船でも大変です。
つい先日、冬の2月に小松島港に向けて北へ航行した際、ちょっとした風から波の高さが一気に2~3mとなり、直後に周辺の漁船はすべて姿を消し、自分の船、1隻だけが潮と風に逆らって航海していました。どうしても帰港しなければならない理由があったため、仕方なく出航したのですが、波の高さが2mを超えてくると、さすがに30フィートの機械船でも波にぶつかるたびに船が高く上に持ち上げられ、直後に海にたたきつけられるという衝撃の繰り返しで、航海速度が通常の5分の1とも言える速にまで減速するだけでなく、舵をきっても功を奏さず、大変な危険を伴いました。
海上交通の本質を知るならば、史書に記されている「海行」と呼ばれる帆船による渡航を、安易に川下りのようなつもりで、1日何十キロも航海できると考えるのは大きな間違いです。大変な危険を伴う帆船による海上交通であるからこそ、悪天候や視界が遮られるだけで航行できない日も多いのです。そして航海には目印が必要であることから、実際には視界の良い日に航海することを原則として、目指す方角を見極めることのできる島や列島から突き出す岬、そして遠くから見える山の頂などを目印として記録し、地理感覚を掴むためのツールとして用いました。また、岬は潮流や風向きが変わるスポットとなり易く、海上交通では陸路の峠のような存在です。よって、邪馬台国へ辿り着くための航路には、いくつかの岬が指標として存在してたと想定されます。こうして時には悪天候に逆潮、逆風が合い重なり、減速を余儀なく強いられことも多々あるという現実を考慮した上で、史書では渡航にかかる日数を平均的に言い表していると考えられます。それ故、海岸沿いを航海するという前提で考えてみても、1日の航行距離は、平均しておよそ15km前後にしかならないと推測されます。
前提8:イスラエルの生活様式との類似点
邪馬台国は山上の聖地であり、新しいエルサレムであるが故に、神の訪れを待つ聖なる場所を汚すことがないよう、邪馬台国には牛、羊、馬などの家畜が存在しなかったことは史書に記されているとおりです。また、邪馬台国では人々が跣で歩き回り、なおかつ、食事も手で食べると記されていることから、その生活様式は大変原始的であったことが窺えます。はたして西アジアからの優れた文化を携えたイスラエルからの移民が邪馬台国の中心的な存在であるとするならば、何故、そのような原始的な様相になりうるのか、考えてみました。
前6~7世紀ごろ、イスラエルの民が日本に移住し、邪馬台国の始祖となったと考えるならば、その生活様式は宗教的背景による影響を多分に受けていると考えられるため、原始的な様相を隠せなかったに違いありません。まず、山を跣で歩く理由は明白です。聖なる山では靴を脱がなければならないという掟がイスラエルにはあるからです。旧約聖書によると、モーセがホレブ山にきて、芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いを見た際、「足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから」という神のお言葉がありました。よって、その教えがいつしか邪馬台国に導入されたと考えられます。
また、邪馬台国では食事は手で食べると史書に記されていますが、これも一見、原始的なイメージであることを否定できません。しかしながら、旧約聖書に含まれている歴史書の記述や、数々の発掘データおよび考古学的見地からの検証から察しますと、古代イスラエル社会においては、食べ物を手で食べるのが当たり前だったようです。当時、祭司によって犠牲が捧げられる際は、食べ物を切るためのナイフと柄杓や、刺したりかき混ぜたりする棒のようなものは使われていましたが(サムエル上2:13-14)、あくまで宗教的儀式が行われる際の話であり、ごく一般的な食卓においては基本的に食物を手で食べていたのです。その風習は、邪馬台国でも長年に渡り継続されたと考えられます。
神の訪れをひたすら待ちながら年月を過ごす山上の国家では、そこが神の訪れる聖なる地であるが故、土地を汚す家畜を飼育することができなかっただけでなく、人が靴さえも履かず、また、食事は手で食べることを常としていたのです。そして邪馬台国を作り上げたイスラエルの民は、山上の国家を造営するにあたり、外部社会から隔離された状態となり、長年に渡り周辺の影響を受けることがなくなりました。そのため、跣で歩いたり、手で食事をしたりするという一見古風で原始的な生活様式が踏襲され続け、その実態を中国からの使者が目撃し、史書に記したのではないでしょうか。