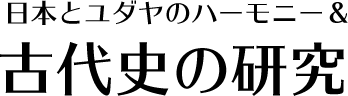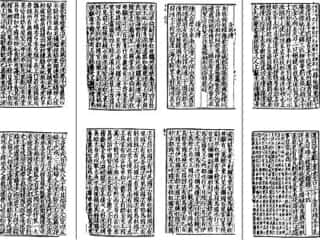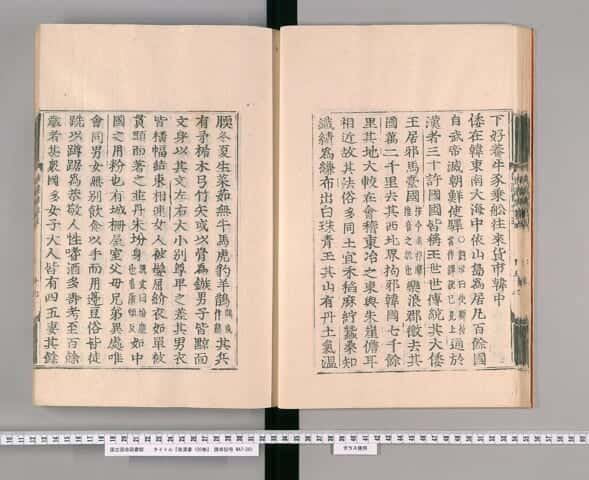疑問が尽きぬ邪馬台国の真相
邪馬台国の存在は史実であり、古代日本史の中核となる重要な位置を占めています。ところが、主に魏志倭人伝や後漢書倭伝などの史書に残されている記述を頼りに邪馬台国を理解しようにも、その解釈には定説がなく、特にその場所については見解の相違が著しいことは周知の事実です。また、昨今の「卑弥呼の墓」の遺跡発掘調査の結果などから、これまで主流となってきた近畿説と北九州説の2大説の内、近畿説の方に、より分があるという方向性が見え始めているようです。しかし、例え卑弥呼の墓の場所が確認されたとしても、邪馬台国を探すための手掛かりにはなるものの、その場所を確定する根拠としてはいささか不十分であり、依然として多分に議論の余地を残すことになります。
一見、歩み寄りが難しそうな邪馬台国の論争ですが、史書をそのまま読み通して文面のとおりに解釈することで、糸口を見出すことができそうです。そのためには、まず日本列島を含む東アジアの歴史の流れを把握することが重要です。そして東夷伝など、中国史書に記載されている倭国に関する記述の中から、歴史の背景にある民族移動の流れなどを理解した上で、邪馬台国の背景に注視することが大切です。
果てしなく続く邪馬台国論争
中国史書には邪馬台国が日本列島のどこに存在したのか、という点については明記されていないことから、比定地が特定できていません。日本古代史上、最大の難題とも言われる「邪馬台国はどこにあったのか」という論争は止むことなく、今日まで定説のないまま続いています。邪馬台国の候補地については畿内説と九州説が有力視される中、その候補地は実際には百か所以上もあると言われ、真相は謎に包まれたままです。
邪馬台国に纏わる歴史の流れを理解するためには、アジア大陸でも特に東アジアの歴史の流れを把握することが重要なのは言うまでもありません。特に秦始皇帝の時代以降に生じた大規模な民族移動や、中国における人口の激減などの史実に目を向けるだけでなく、弥生時代後期より日本列島の人口が急増したという史実にも注視する必要があります。そのような民族移動の流れの中で、いつしか邪馬台国が台頭することになるからです。
邪馬台国はどこにあったか?
特に邪馬台国の場所に関しては疑問点が山積みです。これまでの諸説では、史書は古文書でもあることから、その記述には間違いがあっても仕方ないという前提に立ち、誤植に限らず、方角や距離の誤りや、解釈が難しい箇所は倭国を良く理解していないなどと議論することで、辻褄を合わせる傾向が多く見受けられます。また距離の理解に関しても、九州説などでは放射説のような解釈を用いて、数字の流れに矛盾が生じないよう試みられています。しかし、不自然な流れは否めず、問題の根本的な解決には至っていません。
そもそも楽浪郡の境界から1万2000里も離れていると複数の史書に明記され、中国よりはるか彼方に存在する神秘的なイメージの邪馬台国が、朝鮮半島の目と鼻の先である九州に存在する可能性があったのか、疑問が残ります。実際に北九州地域は、前2世紀から3世紀にかけて朝鮮半島から怒涛のごとく移民が渡来した際に、最初に上陸する倭国の窓口でした。よって、外国からの影響を受けやすかった場所です。外国の侵略から国家を防衛するという見地から考えても、利点があまり見当たらない地域です。また、九州に邪馬台国の土台が育まれてきたとするならば、日本と中国との間で長年にわたりもっと緊密な交流があって然るべきであり、倭国に関する記述も後漢書や三国志の魏志倭人伝のような微量では収まらないはずです。邪馬台国の存在を証明するような遺物も発掘されないことから、真相は究明できないままになっています。
邪馬台国は海に囲まれている島の上にあり、山々が多いとされ、また水行、陸行を混ぜながら朝鮮半島から2か月ほどの期間をかけて渡航する場所にあったことが史書に記載されています。邪馬台国のイメージを神秘に包まれた秘境とも言えるような場所として、古代の識者は捉えていたようです。よって旅の方角や、距離感覚からしても、それが朝鮮半島から目と鼻の先にある九州になるとは想像がつきません。同様に近畿地方の奈良の盆地界隈とも考えにくいのです。大阪湾からの陸路のアクセスがあまりに良すぎるため、どこで下船したとしてもすぐに邪馬台国に着いてしまうからです。ましてや、女王国(邪馬台国)から東へ千里海を渡ると別の島に行けるという記述からしても、邪馬台国の東側には別の島が存在しなければならず、近畿地方を比定地とした場合、その点でも疑問が残ります。
それら中国史書の記述を誤植や識者の間違い、情報不足という前提で解釈する傾向が見られる昨今の状況を踏まえたうえで、今いちど中国史書の記述を元に「邪馬台国への道のり」を再検証することが重要です。そのためには古代の識者が記録した方角や距離のデータをだけでなく、倭国の文化と接して見聞した記述内容を、先入観を取り除きながら、そのまま受け止める努力が前提となります。そして中国史書を執筆した識者の思いに寄り添うように歴史を振り返ると、思いの他、女王国へのルートが見えてくるかもしれません。
中国史書から浮かび上がる邪馬台国の疑問点
過去の歴史を辿る鍵となる中国史書の解釈は難しく、一筋縄ではいきません。また、日本の歴史に名を残している邪馬台国の実態についても、その詳細は確認のしようがなく、多くが謎に包まれています。邪馬台国に関連するさまざまな疑問点や論点については、例えば以下の10項目が考えられます。
- 女王卑弥呼の出自はいかなるものか?皇族に由来するのか?その家系は元来、日本列島を起源に育まれてきたのか、それともアジア大陸から渡来してきた民族に由来するのか?
- 邪馬台国の王は元々男子であったと言われているが、何故、卑弥呼という女王が「相談の結果」立ち上がるまで、互いに攻撃し合い、戦争が続いたのか。また、卑弥呼の後も、男王を立てると戦争になり、再度女王が立てられると平和になったのは何故か?
- 卑弥呼の娘として知られる女王、壹與が3世紀半ばに中国に対して朝貢したのを最後に、およそ150年もの間、史書から倭国に関する記述が見当たらなくなり、「空白の世紀」が生じた理由は何か?
- 邪馬台国の場所は、その長い歴史の中で常に同一の場所になければならないか、それとも時には場所を移動することもあると考えられるか?
- 邪馬台国は中国や朝鮮半島から遠く離れたはるか彼方という印象が強いが、九州というアジア大陸に直近する島という可能性もあるか、また、そこは山上の国か、平野部に広がる国か?
- 魏志倭人伝に「海中の洲島の上に絶在していて、或いは絶え、或いは連なり、一周して戻って来るのに五千里ばかりである」と記載されていることから、邪馬台国は、海に囲まれた大きな島と考えられるが、5千里の距離は何を意味するか?
- 史書に記載されている距離感覚、地理感において、一里はおよそ何kmを意味するか、また、その当時の距離感や計測値は信頼できるデータと言えるか?
- 邪馬台国に辿り着くためには海を渡り、陸を旅するという、いわゆる水行と陸行を繰り返すことになるが、何故、一度船で渡り、そこから内陸に入り、再び海を渡る必要があるのか、また、そうしなければ到達できない目的地とは、どういう地域にあるか?
- 何故、四季を通じて野菜が育ち、温暖であるはずの邪馬台国では、「牛、馬、羊など」の家畜が存在せず、野菜を中心に食しているのか?
- 卑弥呼の高貴なイメージや、古代から語り継がれてきた「君子の国」の在り方とは打って変わり、倭国の人々は「手づかみで飲食し」、「裸足で生活し」、衣服については「ただ結び束ねているだけで、ほとんど縫っていない」、という原始的なライフスタイルを貫いていたのか?
疑問を解く鍵となる中国史書
一見、疑問点が多すぎることから、歴史の流れを理解することが難しく思われます。しかも歩み寄りが難しそうな邪馬台国の比定地に関する論争は、続いたままです。しかしながら、それらの疑問や問題点を解決する鍵となるのが、やはりこれらの中国史書なのです。よって、古代の歴史をできるだけ忠実に記録してきたと考えられる多くの中国史書のメッセージを、ありのままに受け入れて読みながら、歴史の真相の糸口を見出す努力が大切です。
古代の学者は博学であり、単に文字文化が進化を遂げていただけなく、現代人が想像もできないような優れた天文学の知識を持っていました。また、当時の人々はタルシシュ船のような大きな船に乗って世界各地を渡航していた記録も残されていることから、それらの船団が日本列島に到来したと考えても不思議ではありません。よって、中国の識者らは、日本列島を含む世界各地の地勢などについても、かなりの情報を得ていたと考えられています。それ故、中国史書の信憑性は高く、文面のとおりに内容を読み通すことができるという前提で、取り組む必要があります。
今一度、邪馬台国の歴史を振り返るために、中国史書のメッセージをしっかりと読み取り、そこで語られている内容、つまり古代の識者が感じえた邪馬台国の姿、実態について、見つめ直してみましょう。そこから浮かび上がってくる邪馬台国のイメージとは、果たしてどのようなものだったのでしょうか。また、邪馬台国が台頭する以前から、古代の日本は「君子の国」として中国では知られていたことにも着眼し、その背景を探ることも重要な鍵となります。これらの情報から、もしかして邪馬台国の場所だけでなく、邪馬台国のルーツや人々の出自についても理解を深めることができるかもしれません。「邪馬台国の道のり」をとおして、古代史のロマンと真相に近づいて行きます。